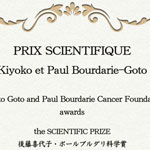受賞者
第13回(2024年度)「後藤喜代子・ポールブルダリ科学賞」
2025.4.1
この度、第13回(2024年度)「後藤喜代子・ポールブルダリ科学賞」の受賞者が決定いたしましたので、お知らせいたします。
| 賞 名 | 後藤喜代子・ポールブルダリ科学賞 (Kiyoko Goto and Paul Bourdarie Scientific Prize) |
|---|---|
| 対象者 |
 坪井 正博 殿 (Masahiro TSUBOI, M.D., Ph.D.) |
| 所 属 | 国立がん研究センター東病院 呼吸器外科 科長 |
| 対象論文 | 完全切除されたEGFR遺伝子変異陽性肺癌に対するオシメルチニブによる全生存期間の延長 Overall Survival with Osimertinib in Resected EGFR-Mutated NSCLC (The New England Journal of Medicine:2023 Jul 13;389(2):137-147.) |
| 選考理由 (中島 淳 諮問委員長) |
坪井先生の論文は、EGFR 変異陽性の非小細胞肺がん (NSCLC) の治療における補助療法としてのオシメルチニブの有効性を実証した画期的な第 III 相臨床試験です。諮問委員全員がこの研究の質の高さと、補助療法としてのオシメルチニブを新しい標準治療として確立する上での役割を明らかにしたことを評価しました。切除された局所進行 NSCLC 患者の無再発生存期間と全生存期間の両方を大幅に延長するオシメルチニブ術後補助療法の確固たる証拠を提供し、再発を待ってからの治療ではなく術後の標的療法を導入するというパラダイムシフトを示しました。この研究は、肺がん治療の進歩として世界的な評価を受けており、特に諮問委員からはこの研究の画期的な性質、強力な臨床的証拠、および分野への影響にコメントされています。さらに、本研究の主著者である坪井先生においては、長年にわたり肺がん研究に対して幅広い専門知識をもとに多大な貢献をされており、臨床腫瘍学における本研究の信頼性と重要性をさらに強固なものにしていることも評価されました。 |
| 受賞者の声 |
きっかけ: 国立がんセンター中央病院での研修を終えて、自分のライフワークのひとつに「肺癌に対する術前・術後補助療法の開発」を掲げ、多施設共同研究などに関わっていた。2002年にはEGFR(上皮成長因子受容体)リン酸化阻害剤であるゲフィチニブを用いた企業主導治験の立ち上げ、実施に関わった。この試験は、開始後間もなくゲフィチニブによる薬剤性肺障害を疑う死亡例を経験し中止となった。2004年にEGFR阻害剤の効果予測因子がEGFR遺伝子変異であることが判明し、EGFR遺伝子陽性肺癌に対するEGFR阻害剤の開発が進んだ。術後補助療法に関しても同様の流れの中にあった。ゲフィチニブを用いた医師主導治験が中国、日本で行われたが、いずれもOSの延長を来す結果に至らなかった。(日本で行われたIMPACT試験には、治験調整医師として参画した。)第三世代EGFR阻害剤であるオシメルチニブが登場し、開発の流れもシフトした。術後補助療法に関しては2013年頃から企業主導で話が持ち上がり、私はこの時グローバル研究代表者の一人に選んでいただきADAURA試験に参画した。 研究の経緯: 試験は2015年11月から2019年2月まで682人(オシメルチニブ投与群:339人、プラセボ投与群=対照群:343人)の患者さんに協力いただいて行われた。 モニタリングのイベント数からランダム化24か月の時点で中間解析が行われ、病期II-IIIA期の患者集団ではプラセボ群の無再発生存割合(再発もしくは死亡していない人の割合:DFS)が44%に対し、オシメルチニブ群のそれは90%で、両群のハザード比は0.17(オシメルチニブ投与が再発もしくは死亡のリスクを83%減じる)であった。IB-IIIA期の集団でも、両群のハザード比は0.20であった。この結果を受けて、2020年10月には米国やヨーロッパの規制当局はオシメルチニブの術後補助療法に対する適応を拡大するとともに、NCCN(米国のガイドラインのひとつ)やESMO(ヨーロッパ臨床腫瘍学会)のガイドラインでもオシメルチニブの術後補助療法を推奨した。OSの解析は、オシメルチニブ群の中間経過観察期間が60ヵ月を超えた時点で行われた。病期II-IIIA期の患者集団ではプラセボ群のOSが73%に対してオシメルチニブ群のそれは85%で、両群のハザード比は0.49(オシメルチニブ投与が死亡のリスクを51%減じる)であった。IB-IIIA期の集団でも、同様にハザード比は0.49であった。この結果から、オシメルチニブによる術後補助療法は、DFSのみならずOSの延長まで認めた。 苦労した点: 日本の規制当局(PMDA)では全生存割合(OS)の延長が術後補助療法の主たる評価項目と定めていたために、OSデータで有用性が証明されない限り適応拡大は認めなかった。ASCO発表1年後、企業がPMDAのために解析結果を公表し、PMDAはOSデータで有効性が示唆される所見から2022年8月に保険承認をした。 一方、日本肺癌学会の肺癌診療ガイドライン2023年度版でもOSの結果が得られるまでは「推奨に至る根拠が明確ではない」とした。この結果では12%の人は「行わないことを推奨」するという判断を下していた。2023年6月のASCO(アメリカ癌治療学会)でOSデータを初めて世の中に公表した。この結果を受けて、漸く日本の肺癌診療ガイドライン2024年度版で「推奨する」形となった。術後補助療法の評価項目としてOSが絶対であるという信者に対して、私はOSのデータを知っていながらASCO発表まではデータを公表できないもどかしさはあった。私は何人もの先生に結果を知りながら半年以上よく我慢できたなと言われたが、PMDAの判断を信じてくれればもう1年早く患者さんのもとへ届けられたのに・・という思いはあった。 今後の応用、発展性について: この結果は分子標的薬の術後補助療法の開発に大いに貢献し、ALK阻害剤でも同様の結果を認めている。 EGFR遺伝子変異陽性肺がんに対する補助療法の開発は、IV期肺がんのそれともに続いていく。既にオシメルチニブより有効な治療方法も開発されている。今の時点では効果と毒性のバランスから補助療法としてはオシメルチニブの有用性は保たれているが、耐性メカニズムの治療開発も含め科学の進歩に期待する。 一方、過去の知見や今回のプラセボ群の成績から手術のみで治る患者さんもII-IIIA期でも30%はいることから、EGFR遺伝子変異陽性肺がん患者さん完全切除例全てに術後補助療法を必要ではないと思われる。切除標本の病理学的所見にLiquid biopsyなどを用いた症例抽出が近々の課題と考えている。今回いただいた顕彰金を本研究の一部に充てたいと考えている。 |
| 賞 名 |
後藤喜代子・ポールブルダリ科学賞 特別賞 (Kiyoko Goto and Paul Bourdarie Scientific Prize -Special Award) |
|---|---|
| 対象者 |
 鵜飼 知嵩 殿 (Tomotaka UGAI, M.D., Ph.D.) |
| 所 属 | ハーバード医科大学 ブリガムアンドウィメンズ病院 講師 ハーバード公衆衛生大学院 デパートメントアソシエイト |
| 対象論文 | 若年発症がんは世界的なエピデミックなのか?これまでのエビデンスと将来の展望 Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implication. (Nature Review Clinical Oncology:2022 Oct;19(10):656-673.) |
| 選考理由 (中島 淳 諮問委員長) |
鵜飼先生の研究は、若年発症がんの世界的罹患率の上昇に着目し、その重大な公衆衛生、社会、家族への影響を強調しています。諮問委員は本研究において、スクリーニング法の改善、環境曝露、若年患者の特有の臨床特性など、寄与要因の徹底的な分析がなされたことを高く評価しています。本研究は、環境、食事、文化の影響に基づく実用的な推奨事項を提供し、的を絞った予防および介入戦略の緊急の必要性を強調しています。本研究は、若年発症がんの発生率増加に対する意識を効果的に高め、その原因と予防に関する研究を優先するよう呼びかけています。さらに、鵜飼先生は、主要な国際的医学雑誌に価値の高い論文を発表するなど、この重要な分野への多大な貢献が認められ、本研究の信頼性と重要性をさらに強固なものにしています。 |
| 受賞者の声 | 若年発症がん(50歳未満の成人発症がん)が増加していることは過去の文献でも報告されていましたが、グローバルな罹患率の分析は行われていませんでした。そこで、我々は若年発症がんのグローバルな罹患率分析を行い、過去数十年間に渡り、乳がん、大腸がん、子宮体がん、食道がん、肝外胆管がん、胆嚢がん、頭頸部がん、腎臓がん、肝臓がん、多発性骨髄腫、膵臓がん、前立腺がん、胃がん、甲状腺がんなど多くの若年発症がんの罹患率が世界中の多くの国や地域で増加していることを明らかにしました。さらに、20世紀半ば以降、多くの曝露因子(食事、ライフスタイル、肥満、環境、マイクロバイオームなど)の有病率が大きく変化し、そのことが若年発症がんの増加に寄与している可能性があることも示しました。さらに、若年発症がんが臨床像や分子病理学的特徴が、高齢発症がんの異なることも記述しました。この論文をまとめるにあたり、共同研究者と1年以上に渡り毎週ミーティングを行い、投稿後も最終的にアクセプトされるまでかなりの時間と労力がかかりましたが、出版後は世界的に注目を集め、多くの論文に引用されました。論文にも記述したように、若年発症がんの増加という重要な課題に取り組むためには、世界中の腫瘍内科医、外科医、疫学者、生物学者、環境科学者、遺伝学者など多くの専門分野の学際的な協力が必要不可欠です。また、本賞の受賞により、若年発症がんの増加という問題がさらに注目され、国際的かつ学際的な協力が進むことを祈っており、私自身もその中心として国際共同研究を主導していきたいと考えています。 |